山形県山形市様
高齢者が多く訪れる山形市の特性にあった窓口の実現。
お互い座ってコミュニケーションが取れることにより目線が合い、
より、聞き取りやすくなった。

左から、邉谷本様、杉本様
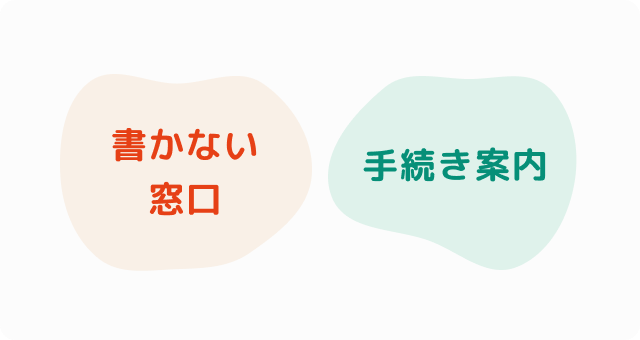
山形県山形市様
書かない窓口、手続き案内の2サービスを導入
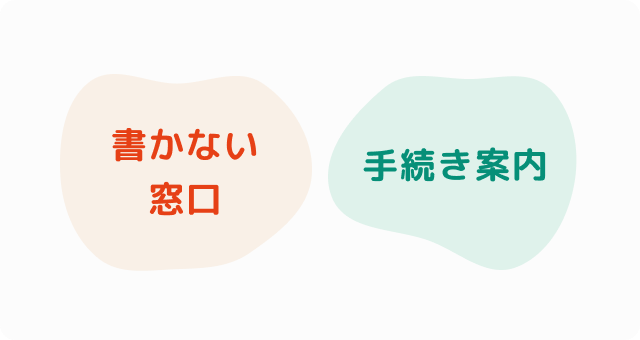
導入効果
山形市様が抱える課題
DX化を進めたいが
高齢者向けの最適な窓口運用が難しい
記入間違いが多く、住民・職員ともに
負担がかかる
手入力が大変
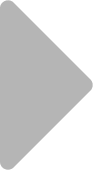

導入による効果
読み取り専用機による確実な情報取得
申請書の記載間違いがない
住民情報システムとの即時データ連携
住民・職員共に座ってじっくりと対応ができる
山形市では2024年1月より書かない窓口・手続き案内の2システムを導入し、運用を行っています。
市民生活部次長(兼)市民課長の杉本様、市民課の邉谷本様に窓口DXソリューション導入の背景と効果について伺いました。
タイミングがうまく絡み合い、大きなめぐり合わせをした
山形市では、2023年度に住民情報システムの更改を実施され日立システムズ社の「ADWORLD」の導入が決定した。
それをきっかけに、窓口での対応や運用そのものの見直しを行うことに着手された。
ー導入のきっかけを教えてください
杉本様:山形市では、2023年に基幹システム(住民情報システム)の更改を行いました。それに伴い、窓口改革(システムの導入)の実施という流れが決まりました。
少し話は逸れますが、世の中様々なことが、どんどん変わってきていますよね。例えば、デジタル化という話だけじゃなく、DX(デジタルトランスフォーメーション)、いわゆるデジタルを使った、色々な新しい価値の創造が行われています。我々市役所でも何かできそうなものはやりたいなと常々思っていましたが…役所の窓口システムや住民の方への対応を変えてしまうには、何か大きな変革や企画、つまりキッカケがないとできないわけです。
そんな中、基幹システムの選定がなされ、日立システムズさんのADWORLDが採択されました。その後、窓口改革に何かいいものはないかと相談をしたところ、日立システムズさんから「こういうシステムはどうですか?」という提案をいくつかお聞きしたのがキッカケとなり、その中の1つが松阪電子計算センターの窓口DXソリューションでした。
何かしらの大きな動きがないと窓口改革はできないので、紹介を受けた時、これは何かすごくいいタイミングの大きな巡り合わせが来たなと思いました。

進まないDX と 市民には難しい申請
山形市の窓口は高齢者の来庁が非常に多く、どうしても記載内容における戸惑いや間違いが多いのが悩みだった。
また高齢者に対してDX化を行うことが、本当に適切な対応となるのかが検討課題でもあった。
ー山形市の窓口ではどのような課題を抱えてましたか?
杉本様:繰り返しになりますが、世の中はデジタル化、つまり「煩雑なものはなるべく技術的に解決していく」っていう流れになっています。それも単なるデジタル処理ではなく、 DX という『デジタルを使った新たな価値を持って一気に進めていく』という流れで進んでいます。
しかし山形市においては、アナログな運用や状況が、この庁舎ができた時から数十年間変わらぬ姿で存在しているものも多く、これは行政では普通のありがちなことですが、民間では様々、やり方が変わっていっていますよね。
最初、日立システムズさんからの提案は「市民の方が直接タブレットを操作するのはいかがでしょうか?(※市民操作型)」というものでした。それは紙に書くよりも、デジタル化を進めるという意味では一歩進むことは間違いないとは思いました。ただ、市民がタブレットを操作するっていうのは、ペンで紙に書いているものを紙ではなくて、タブレットに変えて書いているだけなので、同じだと思いました。そこの部分はやっぱりやめたいな…と、そういう思いが当時ありました。
※市民操作型…住民がシステムを操作し入力する方法 / 職員操作型…職員がシステムを操作し入力する方法

邉谷本様:例えば、住所異動の日付や、住所の書き方など自治体ならではのルールがあり、そういったルールは市民の方にはどうしてもわかりづらく、高頻度で間違えて申請される箇所が存在します。錯誤の届出にならないようその分、職員も注意して見なければいけないし、お客様とより慎重にお話をしなければいけないので、思った以上に受付に時間がかかるということがありました。
中には個性的で読みにくい字もあり、確認の上、補正しなければいけなかったり、市民が記入する申請書を間違われてしまい「もう1回書いてください」とやり直しをお願いすることによって、お客様とトラブルになることもあったので、そういう点をなくせたらいいなと思っていました。
また、私は、入庁1年目から市民課配属ですが、周りの自治体が既に「デジタル化」「DX化」を推進し、マイナンバーカードの利用も主流になってきていた中で、山形市ではマイナンバーカードを使わず、地道に手作業で入力している姿がすごく残念に感じて…マイナンバーカードを使って異動入力や入力補助をされている自治体がすごく羨ましく思っていました。

山形市の特性に合った職員操作型システムだからこそ採用
ー弊社のシステムを選んでいただいた決め手をおしえてください。
邉谷本様:当初、市民操作型を導入したいと思っていたのは、正直言うと、やはり聞き取りしながら職員が全部手入力をすると時間もかかり大変なので、お客さん自身が自分で届出書を打ち込みで作っていただいたり、デジタルが使える人はご自宅などで事前に申請書を作る事前申請書作成アプリみたいなものを導入する方が、市民の方が入力したデータを取り込むだけなので、市民の方も職員もお互いにメリットになるよね…と思っていました。
しかし、日立システムズさんから提案を受けた後に、職員操作型と市民操作型のそれぞれの自治体へ視察に行った際に、市民操作型では山形市の窓口は変わらないと思いました。それは日立さんの(タブレットを使った)システムだからという訳ではなく、職員操作型のほうが絶対、山形市民の特性に合う…と。

山形市の窓口に来る方の割合は高齢者が多く、市民操作型では一人で操作するのが難しくて、職員がサポートしないと利用できないだろうという点があり、それならば市民の方の手続きが楽になり、かつストレスなくこなせる職員操作型がいいだろうなと考えを変えました。また、松阪電子計算センターさんの『書かない窓口』であれば、マイナンバーカードや免許証の情報を読み取って自動入力(入力補助)できるので、職員操作でも大丈夫という評価に変わりました。
加えて、取り込んだデータが住基システムに連携入力ができ職員負担が軽減されること…これはできてほしいっていう最低限な条件をクリアできた点も採用のプラスになったと思います。
先例紹介による早期の問題解決でスピーディーな導入へ
ーシステムの導入を行うにあたり、ご苦労された点などはありましたか?
邉谷本様:山形市の場合、実のところ、システムを決めてから導入までの時間が本当に短かったので、やはり庁内で要件を詰めるのと、運用や操作のイメージを持つ時間が少なかったのが大変でした。
しかし、他の導入自治体の様式はこういう感じですとか、要件定義についてもこういう判断をしていますという事例を最初に頂けて、山形市がゼロから考えていたら間に合わなかったと思いますので、このような対応は助かりました。
新しいシステムに触れる期間も短かったですけれど、色々調整頂いて、なるべく早く触れるようにシステムを準備してもらい、職員も手が空いたら、とりあえず新しいシステムの操作に慣れようという感じで、時間を無駄にしないよう努めました。
また、職員から寄せられた分からないところを松阪電子計算センターさんに質問しました。それに対してすごく早く返答して下さいましたし、要件定義においても、「できる・できない」というところも迅速に詰めて下さったので、短期間による調整などの苦労というのはありましたが、スピーディーに動いて頂いた所も、すごくありがたく思っています。
住民の方から「書かなくていいの!」「これだけでいいの?」と言われる窓口に
ーシステム導入後、どのような効果がありましたか?
邉谷本様:マイナンバーカードのICチップから情報を読み取れるので、基本4情報(※)の入力に関してはすごく便利になりました。入力が大変だった前住所や、外国籍の方の氏名も読み取ってくれますので、マイナンバーカードを使えるシステムという点ですごく便利になりました。
市民の方については先程も述べたように、山形市の窓口に来られる方は高齢者が多いので、1枚の申請書を書くだけでもすごく負担になり、記入間違いによる訂正や、同じことを何枚もの申請書に書かせるというのは大変な思いをさせてしまっているなと感じていました。
しかし今は、職員が作成した届出書の内容を確認してもらい署名と電話番号のみの記載なので、必要最低限の所に記入だけなら市民の方も楽、かつ時間も早くなりました。書く要素が減る分、職員にとっても(確認が)簡単になり、スピーディーに対応でき、書き直しをお願いすることもなくなりました。
1つのことが解決することにより、市民も職員も負担が無くなったという感じですね。
来庁された方からも「あれ、市役所変わったね」という話をされる方はすごく多くて「記載台がなくなって、職員の方で全部書くので、お話だけ聞かせて下さい」という形で進めていくと、やはりお客さんからは「え、これだけでいいの?」「書かなくていいの?」とすごくびっくりされる方が多いです。
※基本4情報…氏名・住所・生年月日・性別
杉本様:やはり(流れが)すっきりしますよね。また、記載台って結構大きいんですよ。市民課前だけでも1台に6~8人ぐらいの人が使えるスペースのものが6台ありました。その分が、物理的に無くなって、そこに待合の椅子を置けるようになりました。椅子を置いたとしても、今までよりはかなりすっきりした印象になりましたね。

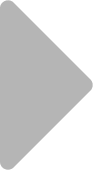


邉谷本様:以前は住所異動に関してはローカウンターが1窓口、ハイカウンターが4窓口という構成でしたが、それをすべてローカウンターに変更して9窓口に変えました。これによって住民の方と職員がお互い座ることになり、目線が合ってコミュニケーションが取りやすくなりました。今までは、職員が座ってお客さんが立って受付という状態だったので、どうしても職員はお客さんを見上げながらの接遇になってしまい、お互いに疲れてしまう体勢でした。
今では、同じ目線で話せるので…窓口の雰囲気が良くなった気がします。お客様は長時間立った状態での受付になると、どうしても疲れてしまい、こちらが聞いていることに対して、「はい」の返事なのか、「いいえ」の返事なのか、ちょっと聞き取れないような時もありました。今は、座って落ち着いた状態、リラックスした状態でお話し頂いているので、確実に確認すべきところを、しっかり聞けるようになった感じがしています。
手続き案内表も、以前は全員一律書式のチェックボックス付きの案内をお渡して、ご自身で該当のあるところを回って下さいという案内で、こちらから「該当のここに行く必要がありますよ」という説明はもちろんするのですが、それでも「どこが必要なんだっけ?」と市民課に戻ってこられる方もいらっしゃいました。また、職員によっては経験年数により案内漏れしてしまったり、案内しなくていいところを案内してしまう恐れもありました。しかし、システム導入したことで資格や年齢から自動判定できるので、その人に必要な手続きだけを記載した専用の案内表が作成できます。迷わない窓口としてお客さんが次どこに行けばいいか一目で分かるというメリットもありますが、職員においても案内漏れや他の案内をしてしまう案内ミスが減りサービス向上に繋がったと思います。



杉本様:山形市以外の他の自治体の窓口を大方知っている訳ではないですけど、この窓口DXソリューションは、多分どこ(の自治体)であっても、非常に効果が感じられるものとして導入された側は満足されるのではないかなと思います。
稼働日の1月4日は、私自身、やはりドキドキしていました。システムが変わるというのは、やっぱりちょっと怖いじゃないですか?しかも、その日は長期の休み明けで、お客さんも沢山来る。ですから、私としては少なからずトラブルなどがあるのではないかと思っていました。
しかし、当日は松阪電子計算センターさんも山形市に待機し、何かあったらすぐ対応できるような体制をとって頂いていましたが…何もなくスムーズに流れていく! 上手くいって当たり前なんでしょうけれど、逆にこれほど上手くいったことが私の中では想像以上だったのでちょっと驚いてしまいました。
ですから、山形市と同じようにご高齢の方が多く、また待合スペースで悩まれている自治体などには、もちろんオススメできますが、それ以外の自治体にも広く、一般的にもおすすめできるシステムだと思っています。
書かない窓口の申請範囲の拡充をめざして
ー今後の展望についてお聞かせください
邉谷本様:山形市では、現在、窓口DXソリューションの来庁目的の機能を一部のみに制限をかけています。例えば、「おくやみ窓口」を山形市は実施しているのですが、現在は職員がExcelで届出書の作成を行なっています。しかし、窓口DXソリューション「書かない窓口」の来庁目的には『おくやみ』というのがあるので、(山形市では現在未使用ですが)、ゆくゆくはおくやみ窓口や、出生届に関連した案内などにも使えるように「書かない窓口」「手続き案内」の範囲を広げていけたらいいなと思っています。
ー貴重なお話ありがとうございました。
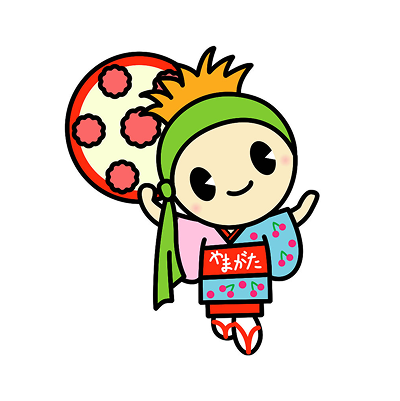
山形県山形市
人口約25万人の山形県の県庁所在地である山形市。
樹氷と温泉で名高い「蔵王」や、松尾芭蕉ゆかりの「山寺」などの観光地を有し、自然が豊かで都市機能も充実している暮らしやすいまちである。
こうした中、山形大学医学部東日本重粒子センターにて世界的に誇れる次世代重粒子線がん治療が受けられるほか、人口10万人当たりの病棟数及び医師数が東北中核市で一番多いなど「医療」に強みを持っていることから『健康医療先進都市』を推進している。
また、「花笠まつり」や「日本一の芋煮会フェスティバル」、「山形国際ドキュメンタリー映画祭」の他、音楽や食など多彩で豊富な文化を背景に、2017年には、ユネスコのCreative Cities Network(ユネスコ創造都市ネットワーク)にも映画部門で認定されるなど、芸術文化を産業振興・観光振興・教育振興に活かした『文化創造都市』の実現を目指している。
